|
(1)健保法等の改正のポイント
●健保法等の改正のポイント
《平成14年10月実施分》
- 老人保健の対象年齢を70歳から75歳以上に引上げ。(段階的実施)
- 老人保健法による医療に対する公費負担割合の引上げ。(段階的実施)
- 70歳以上の高齢者の一部負担金は入院・入院外とも定率1割負担。
(老人保健対象者以外も含む)
- 定額制および一部負担金上限制の廃止。(老人外来一部負担金)
- 所得が一定以上の70歳以上は、入院・入院外とも2割負担。
- 老人保健の対象外の70〜74歳は、保険者から新たに「高齢受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。
- 老人保健対象者には、市町村から「医療受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。
- 70歳以上の高齢者には、高額医療費(療養費)制度を適用。
- 窓口負担の除外規定:
- 入院患者、寝たきり老人在宅総合診療料または在宅末期医療総合診療料算定患者は限度額を超えた一部負担金徴収なし。
- 3歳未満の乳幼児の自己負担は、入院・入院外とも2割負担。
《平成15年4月実施分》
- 3歳〜69歳は、入院外来共 3割負担(国保組合の一部を除く)
- 薬剤一部負担金制度は廃止
- 55歳以上退職の任意継続被保険者期間の特例廃止となり2年間まで
- 継続療養給付の廃止
《平成15年6月実施分》
- 再診料、外来管理加算、外来診察料の月内逓減制の廃止 (詳細)
●一部負担金・自己負担額の見直し
- Ⅰ.70歳以上は
- (1) 一部負担金(入院・入院外とも)
-
- ① 一定以上所得者:定率2割
- ② 一般・低所得者:定率1割
- ・従前の月額上限・診療所の定額制は廃止
- ・昭和7年10月1日以後生まれは75歳になるまで医療保険の医療
- ⇒「高齢受給者証」対象者(健康保険の点数表)
- ・昭和7年9月30日以前生まれは老人保健の医療
- ⇒「老人医療受給者証」対象者(老人保健の点数表)
-
※70歳以上(高齢者)は
老人保健法対象者 「老人医療受給者証」と
70歳〜74歳の「高齢受給者証」対象者に分かれます
※点数表が違うので注意
- ・65歳以上の寝たきり等の状態にある者の取扱いは 従来どおり,市区町村長の認定により「老人保健対象者」 として取扱う
- ・入院及び在宅総合医療等の場合、一部負担金徴収限度額がある。
-
- (2)一部負担金徴収限度額
- * 入院、寝たきり老人在宅総合診療料または在宅末期医療総合診療料算定患者さんに対する1ヶ月の一部負担金の額が次の金額に達した場合、その医療機関ではそれ以上は徴収しない
|
|
入院 |
在総診、在医総 |
70
歳
以
上
の
高
齢
者 |
一定以上の所得のある高齢者 |
72,300円+((医療費ー361,500円)×1%) |
40,200円 |
| 一般の高齢者 |
40,200円 |
12,000円 |
| 市町村民税非課税世帯の高齢者 |
24,600円 |
8,000円 |
| さらに一定の所得に満たない高齢者 |
15,000円 |
8,000円 |
- (3)70歳以上の高額療養費の新設
-
- ・70歳以上に適応される自己負担額限度額設定
Ⅱ、一般医療保険対象者( 70 歳未満)
- 1. 一部負担金
-
- ① 3歳〜69歳は平成15年4月より、3割負担(国保組合の一部を除く)
- ② 3歳未満は2割負担
- 2.高額療養費
-
- ① 自己負担限度額の引き上げ(別紙参照)
- ② 制度の考え方に変更なし
- ③ 高額となる特定疾病患者の負担軽減
- (従来どおり:70歳以上も共通)
-
自己負担限度額10,000円/月
[対象疾病]
・ 人工腎臓を実施している慢性腎不全
・ 血漿分画製剤投与の先天性血液凝固因子障害
第Ⅷ因子障害・第Ⅸ因子障害
・ 抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群
3. , , , , , ,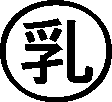 (東京都のみ) (東京都のみ)
- ・
 は全対象者が一割負担で 一部負担金徴収限度額がある。 は全対象者が一割負担で 一部負担金徴収限度額がある。
-
- ・
 、 、 、については 、については   表示の医療証持参者は一割負担で 一部負担金徴収限度額がある 表示の医療証持参者は一割負担で 一部負担金徴収限度額がある
-
 表示のみの医療証持参者は入院・外来の一部負担なし 表示のみの医療証持参者は入院・外来の一部負担なし
-
- ・
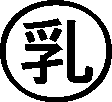 は入院・外来の一部負担なし は入院・外来の一部負担なし
|
|
|
|
●一部負担金徴収額等(東京都)
|
※H15.4.1から
|
一部負担徴収額(入院外来とも) |
点数表 |
70
歳
以
上
の
高
齢
者 |
「老人保健法」対象者
H14.9.30までに70才になっている人,或いは65才以上で市町村長の認定により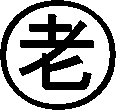 の人 の人 |
一定所得以下 |
1割 |
老人
|
| 一定所得以上 |
2割 |
「高齢受給者証」対象者
H14.10.1以降に70才に70才になる人(75才になれば「老人保健法」対象者) |
一定所得以下 |
1割 |
一般
|
| 一定所得以上 |
2割 |
6
才
以
上
70
才
未
満
の
人 |
 は全対象者 は全対象者 |
1割 |
一般 |
| 社保 |
3割 |
一般 |
| 退職 |
3割 |
| 国保組合 |
2〜3割 |
| 上記以外 |
3割 |
| 3才から6才未満 |
3割 |
一般 |
| 3才未満 |
2割 |
一般 |
|
一部負担金徴収限度額
|
|
入院 |
在総診、在医総 ※
|
70
歳
以
上
の
高
齢
者 |
一定以上の所得のある高齢者 |
72,300円+((医療費ー361,500円)×1%)
|
40,200円 |
| 一般の高齢者 |
40,200円 |
12,000円 |
| 市町村民税非課税世帯の高齢者 |
24,600円 |
8,000円 |
| さらに一定の所得に満たない高齢者 |
15,000円 |
8,000円 |
|
|
入院 |
外来 |
 |
 一般 一般 |
40,200円 |
12,000円 |
| 市町村民税非課税世帯 |
24,600円 |
8,000円 |

 |
一部食表示の医療証持参者 |
40,200円 |
12,000円 |
※ 寝たきり老人在宅総合医療又は在宅末期医療総合医療を受けている場合が対象になります。
 ,、 ,、 、 、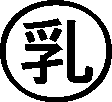 請求については、現行通り社保は10名連記請求書で、国保はレセプト請求 請求については、現行通り社保は10名連記請求書で、国保はレセプト請求
参考:
H15.4.1以降の変更点
①一部負担金徴収額は3才から70歳未満まで3割に統一。(   の の  表示の医療証持参者は一割) 表示の医療証持参者は一割)
②外来薬剤一部負担金は制度はすべて廃止
③55歳以上退職の任意継続被保険者期間の特例廃止となり2年間まで
④継続療養給付の廃止
 一部負担金徴収額一覧表PDF(東京都) 一部負担金徴収額一覧表PDF(東京都)
|
|
●高額療養費の見直し
①70歳未満の高額療養費の見直し
・一般と上位所得者の自己限度額引き上げ
・一般と上位所得者の合算対象基準額の引き下げ(30000円→21000円)
70歳未満の人の自己負担限度額(参考)
|
|
平成14年10月〜平成15年3月 |
平成15年4月〜 |
70
歳
未
満
の
人 |
上位所得者 |
139,800円+
(医療費−699,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
多数該当 77,700円 |
139,800円+
(医療費−466,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
多数該当 77,700円 |
| 一 般 |
72,300円+
(医療費−361,500円)×1%
合算対象 21,000円以上
多数該当 40,200円 |
72,300円+
(医療費−241,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
多数該当 40,200円 |
| 低所得者 |
35,400円
合算対象 21,000円以上
多数該当 24,600円 |
35,400円
合算対象 21,000円以上
多数該当 24,600円 |
|
|
②70歳以上の高額療養費の新設
・70歳以上に適応される自己負担限度額設定
70歳以上の人の自己負担額(参考)
|
|
|
平成14年10月〜 |
70
歳
以
上
の
人 |
所得区分 |
自己負担額
(すべての自己負担額を世帯で合算)※2 |
|
外来(個人ごと)※1
|
|
| 一定以上所得者 |
40,200円 |
72,300円+
(医療費ー361,500円)×1%)
多数該当 40,200円 |
| 一般 |
12,000円 |
40,200円 |
| 低所得者(住民税非課税=世帯主・世帯員全員が非課税 |
Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| Ⅰ |
15,000円 |
※1 ここでの自己負担額とは、同一月・個人単位で医療機関や金額を問わず、
外来の自己負担すべてを合算した額
※2 ①金額を問わず自己負担額すべてが合算の対象
②外来分は個人単位の外来の限度額を適応した後、なお残る自己負担額
③入院分は、限度額超えた分の現物給付があった場合でも、限度額適応前の自己負担額を合算
④老人医療対象者と70歳以上75歳未満高齢者との世帯合算は出来ない
●70歳以上75歳未満と70歳未満の世帯合算の新設
健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が構成
している世帯については、同一月に70歳以上と70歳未満それぞれの負担が
ある場合には合算を行うことが出来ます。
世帯合算の対象となる負担額は、70歳以上ではすべての負担額、70歳未満
では各21、000円以上(70歳未満での合算対象基準額と同じ)の負担額です。
|